取材:2017年6月

片山翔平(かたやま・しょうへい)
2013年、視覚伝達デザイン学科卒業。
武蔵美時代に培った、多角的なものの見方や解釈が評価されて、株式会社資生堂に入社。
現在は同社の『グローバル資生堂』チームでアルティミューン、資生堂 メーキャップといった人気ラインのコミュニケーション・ツール制作に関わっている。
日本で一番“美しいもの”を
つくってきた会社だから
関西に生まれ、手塚治虫に憧れて漫画家をめざしていた少年が辿り着いたところ。それは日本を代表する化粧品メーカー・株式会社資生堂だった。男性向けのラインもあるが、やはり女性向けコスメの印象が強い同社を志望した経緯について、片山さんはこう振り返る。
「最初は広告代理店なども検討していたのですが、最終的にはメーカーに行きたいと思うようになりました。自社で商品をつくり、宣伝し、販売する…中でも資生堂は、日本で一番美しいものづくりをしてきた、とことん美を突き詰めてきた会社で、ああ、ここに入りたいなと思いました」。
商品づくりはもちろん、デザインや広告表現の分野でも、常に日本をリードしてきた同社らしいエピソードがある。
「入社してまず学んだのは“資生堂書体”という、独自の書体について。独特のカーブや線の強弱を、よく見て、何度も描いて、頭と体に叩き込みました」。
新たなものを生み出すためにも、まず自社の伝統を知ることから、キャリアがスタートするのだ。
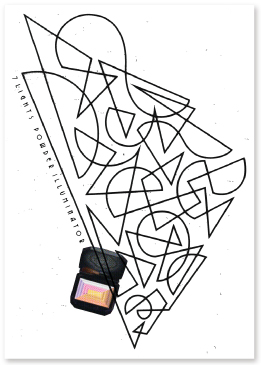

バックボーンの豊かさこそが
人の心を震わせる
「資生堂の場合、たとえば新たなブランドやキャンペーンを立ち上げるときには、とにかく徹底的にリサーチをします。新色の口紅をPRするとしたら、原料となる紅花の栽培史、製法の変化、紅を詠んだ文学作品など、広告にはまず使われないだろうという情報でも収集する。そういう点は、“なぜ?”という根拠に基づいたデザインを求められる武蔵美の手法とよく似ていると感じました。
テーマのバックボーンを深く理解した上で、表現を考え抜くというのが、資生堂の伝統的なスタイルなんです」。
妥協のないリサーチに裏付けられた、これが“自分たちの考える美しさだ”というこだわりをもって、資生堂は業界を牽引し続ける。近年、同社の海外向けブランド『GLOBAL SHISEIDO』が絶好調なのも、日本製品への高い信頼に加えて“日本の美”を感じさせるプロモーションが、世界市場の注目を集めているからだろう。
現在、片山さんはこのチームの一員として、多忙な日々を過ごしている。CM、ポスター、POP、デジタルメディア…製品を世に出すためにつくられる多彩なツールを、資生堂では“コミュニケーション”と総称しているが、それらの芯を貫く戦略は、まさにチーム総員によるリサーチや意見交換から生み出されていくのだ。
「製品ごとにモデルやトレンドの違いはあれど、花椿のマークが入った瞬間に、それは資生堂の広告になります。言語や文化の異なる海外でも通用するブランド力は、長い時をかけて確立されたもので、とてつもない価値があるんです。伝統を尊重し、そこに関わる責任と誇りを持ちながら、革新性のあるアイデアを突き詰めていけたら」。
数少ない男性デザイナーとしての視点で美を追求しながら、片山さんは資生堂のDNAを受け継いでいく。

上司が語るムサビの人間力

フレッシュな風を生む存在に
宮岡 知子
宣伝・デザイン部
グローバルコミュニケーションデザイン室
グループリーダー/チーフクリエイティブプロデューサー
資生堂において“革新性”とは、ブランドニューではなく、フレッシュという意味合いで用いられます。長い伝統のよさを活かしつつ、フレッシュな価値観や表現を加えるべく努力する。それが当社のデザイナーの使命です。片山さんは、チームを超えていろんな人とコミュニケーションをとりながら、自分なりの提案をしかけようという意欲がある人。次代の資生堂に、新たな風を生みだしてくれたらと期待しています。
企業リンク
> 株式会社 資生堂



